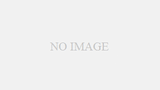法人にすると手続きが増えます。面倒だな・・と思ったことを挙げてみます。
社会保険関係
国民健康保険、国民年金は勝手に振込額が決まって通知されるのでラクです。
国民健康保険は前年に確定申告していれば、その数字を元に6月に切り替わりますし、国民年金は定額です。
どちらも口座引落の手続きをしておけば勝手に口座から引き落としされます。
これが法人となると社長本人が設立やら算定基礎届などしなければなりません。
法人は社長自らに給料を出して、給与所得控除を受けられるのが税制上のメリット。
ですが算定基礎は毎年あります。給料の額が変動していれば、毎年同じにとはいきません。
給与計算
社会保険にも絡んできます。
社会保険料と源泉税を引いて、社長自らに給料を支払います。
支払わなくても計上するだけでもOK。その場合は未払金が貯まっていきます。
社会保険の金額も数円変わったりします。「あれ?先月と数円単位で違うぞ・・」と感じたことも。
自らの給与計算であればミスしても問題にはなりませんし、支払わなくても大丈夫です。
私も自分の給料はずっと未払のままです。
源泉税
給料から引いた源泉税を税務署に納税します。
これもまためんどくさいです。
・7月10日まで
・1月20日まで
の年2回が一般的です。
たとえば月の給料が8万円であれば、源泉税はゼロ円です。
ゼロで申告だけすれば良く、納税はする必要がありません。
これなら少しラクですが、申告の手間はかかります。
法定調書の提出
1 「給与所得の源泉徴収票」は、俸給、給料、賃金、歳費、賞与その他これらの性質を有する給与の支払をする方です。
2 「退職所得の源泉徴収票」は、法人の役員に対して退職手当、一時恩給その他これらの性質を有する給与の支払をする方です。
ただし、死亡退職により退職手当等を支払った場合は、相続税法の規定による「退職手当金等受給者別支払調書」を提出することになりますので、「退職所得の源泉徴収票」は提出する必要はありません。
3 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号ならびに所得税法第174条第10号および租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金および賞金の支払をする方です。
※国税庁
法人にして自らに給料を支払い、各士業に報酬を支払ったら税務署に提出することになります。
ひとりで活動する個人事業主であれば、提出しなくていいものです。
これも手間ですね。
さらに市区町村にも提出するものがあります。
法定調書の提出義務者は、「給与支払報告書」および退職所得に係る「特別徴収票」をそれぞれ所定の市区町村に提出する必要があります。
まとめ
法人にすると給料系の手続きがめんどくさいと感じます。
税金対策は分かりやすいのですが、このあたりのめんどくささは気にされてない方が多い印象です。