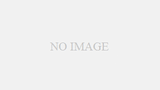お客様と確定申告の打合せをしています。
確定申告書の「㉚課税される所得」の下に税額が表示されます。「㉛上記㉚に対する税額」として。
ここから定額減税、住宅ローン控除、予定納税、源泉徴収税額などを引いて、最終的な納税額や還付額が分かります。
㉛÷㉚で実質の所得税率が分かります。この税率に住民税の約10%を乗せたものが実際の税率とも言えます。
さらに事業税、国民健康保険、国民年金まで入れるかどうか。
さらにさらに消費税まで含めるか。
消費税をどのように式に組み込むのか分かりませんが・・
所得税、住民税の実質税率で41.6%の方がいました。
結構、稼ぎは多い方です。
これに「年間消費税額÷㉚課税される所得=10%」
41%+10%=51%
2年前の収入が5,000万円を超えており、消費税の計算方法が簡易課税が使えませんでした。
それもあって消費税が高くなり、結果的に税率全般を上げる要因に。
私の場合はサラッと計算してみたところ40%弱でした。
所得税、住民税、消費税(簡易課税)、個人事業税で計算。
健康保険、厚生年金を入れたらどこまで行くのか。
Xでフォローしていますし、本も読んでいる方のポスト👇
何度も言うけど、国民負担率は50%近くになっている。公共料金とか別勘定の税金を含めると60%を超える。これだけ負担率が高い国はどこも医療費や学費が無料だったり、年金が手厚かったりするけど、日本はぼったくられるだけ。国民が羊のように大人しいからやりたい放題だよ。https://t.co/KCSgOlRXYJ pic.twitter.com/z0pm1hG1Vx
— まりなちゃん (@t2PrW6hArJWQR5S) January 23, 2025
所得税率だけで考えてはいけないということですね。
このお金がどこに流れているのかまでを確認しなきゃいけないのでしょう。